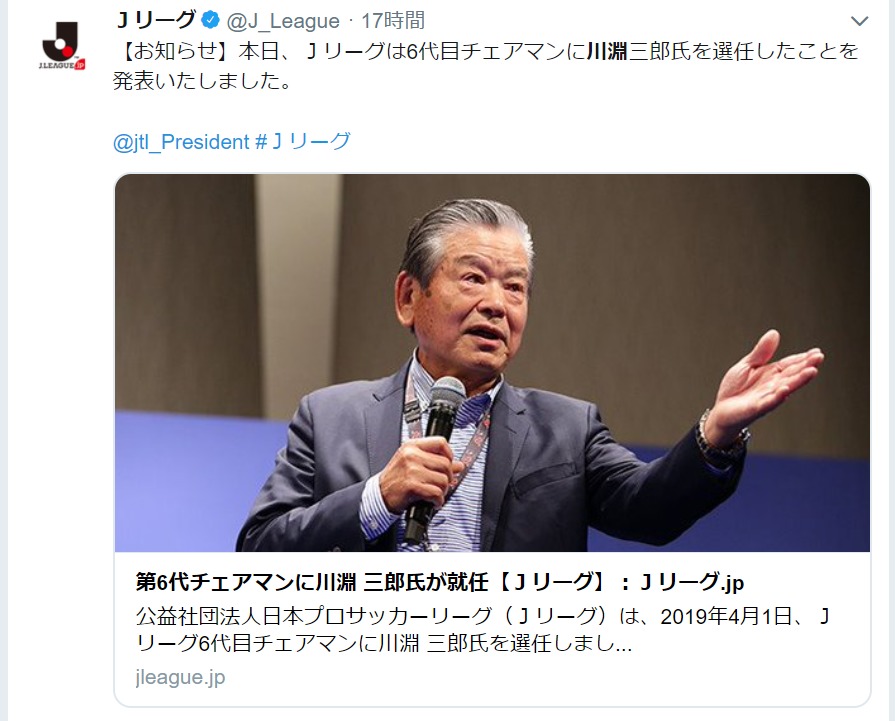【Jリーグ】コンタクトプレー問題でJFAの扇谷審判委員長「意図的に時間を伸ばすためにファウルをとらないということは決してありません」
 今季2回目のレフェリー(審判)ブリーフィングが行われた。(C)SAKANOWA
今季2回目のレフェリー(審判)ブリーフィングが行われた。(C)SAKANOWA
レフェリーブリーフィングで、「アクチュアルプレーイングタイムを伸ばすために、何か判定を変えたということは一つもありません」。
日本サッカー協会(JFA)は3月18日、レフェリー(審判)ブリーフィングを開き、2025シーズン開幕から1か月が経過したなか、これまで話題になってきた「コンタクトプレー」に関して、JFA審判委員会の扇谷健司委員長、佐藤隆治 審判マネジャーが、これまでの傾向など審判サイドの立場から説明した。
2025シーズン、Jリーグがアクチュアルプレーイングタイムを伸ばすことを目標に掲げるなか、野々村芳和チェアマンもプレー強度を求めてきた。そのために反則を取らなくなり、選手が傷つくプレーが増えたのではないか――。
その点について、扇谷委員長は次のように語った。
「アクチュアルプレーイングタイムを伸ばすために、何か判定を変えたということは一つもありません。たまにそういった記事を拝見し、こうした機会で話せていただきたいと思っていました。決して競技規則が変わったわけでもなく、意図的に時間を伸ばすためにファウルをとらないということは決してありません」
一方で、扇谷委員長はJFAとJリーグの総意として、「全体の判定の標準を上げていきたい思いはあります」とも説明する。
「日本代表が2050年までにワールドカップ優勝を目標に掲げるなか、審判員にとってもチャレンジになっています。我々がレフェリーに伝えているのは、反則でないことに笛を吹くのはやめよう、ということです。レフェリーはベストを尽くしますが、振り返る際、この反則で笛を吹くの? これは何の反則なのか? ということが、これまでもありました」
「標準を上げる際、そういった反則でないことに笛を鳴らすのはやめよう、そのためのトライをしようとレフェリーたちには伝えています。逆に反則には笛を吹き、プレーを続けるのであればアドバンテージを採用しよう、と。ただ本来反則で取るべき時に、笛が吹かれなかったことはあったと思います。それに関しては、今シーズンから急に笛を吹かなくなったわけではありません。これまでも当然ありました」
プロフェッショナル・レフェリーのキャンプでも、審判委員会からは「反則に関しては、しっかり取ろう。プレーを続けさせるのであればアドバンテージを採用しようと。その見極めをしっかりしようと伝えています」ということだ。
「レフェリーもいろいろ考えて、何とか期待に応えようと取り組んでくれていてその姿勢には満足しています。一方、改善しないといけないこと、それは当然必要になってきます。そこはしっかり(ファウルを)取ろうということにトライしています」
例えばリスタートを早めることなど、審判サイドで“反則をとる、とらない”ではなく、アクチュアルプレーイングタイムを伸ばすための協力は、もちろんしていくということだ。
「日本の象徴であるJリーグがより魅力的になるように、私たちレフェリーサイドで何ができるかは常に考えています。私たち(審判)ができることはあります。ただ、それは反則をとらないということではありません。例えばリスタートを早くする、選手交代や負傷による時間を短縮することなども挙げられます」
そのように、あくまでも判定基準を変えたわけではないことが強調された。審判員も「様々な微調整を行っている」(佐藤氏)という説明があった。
関連記事>>【Jリーグ】プレータイム増のためファウルを流す!? 判定基準は変わっていないのでは。審判以上に選手側の質や問題も
また冒頭、中国で開催されたU-20アジアカップ決勝で、笠原寛貴主審、聳城巧副審と日本人の審判団が担当したことが報告された。近年のアジアの大会の決勝で日本人が主審を担当したのは、2016年ACLの決勝セカンドレグで佐藤氏が主審を担当して以来となった。