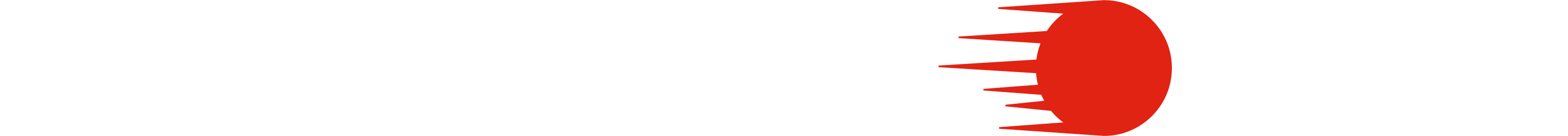恐ろしく視野の狭かった長友。反町『監督』がJFAに提出した「北京五輪レポート」を明かす
 長友佑都。写真:兼村竜介/(C)Ryusuke KANEMURA
長友佑都。写真:兼村竜介/(C)Ryusuke KANEMURA
JFAの技術委員長連載コラムで、大卒選手や街クラブ出身…興味深いプロへの道筋のデータとともに。「今の長友とは別人だった。本当に〝若葉マーク〟」
日本サッカー協会(JFA)の反町康治技術委員長が3月1日、JFA公式サイトでの連載コラム『サッカーを語ろう』第27回「パスウェイ」(子供からトップ選手になるまでの道筋) を公開した。反町委員長らしく、詳しいデータとともに考察。監督として戦った2008年の北京オリンピックでの長友佑都のパフォーマンスについて、当時JFAに提出したレポートの内容を明かしている。
日本代表の強化責任者である反町委員長は、カタール・ワールドカップ(W杯)日本代表メンバーのパスウェイについて紹介。中山雄太(柏レイソルユース出身)を含めた27人のうち、9人が大学経由、そして2種(高校年代)では、高体連組13人、Jクラブアカデミー出身13人、街クラブ(三菱養和サッカークラブユース)出身が1人(相馬勇紀)だった点に触れ、「これほど大学に進学してプロになる選手が多い国は日本くらいだろう」「代表選手のユース年代の育成ルートが複線化している」として、次のように分析している。
「日本の代表選手の大半は一番身近な地元の少年団やスクールなどでサッカーを始め」「ジュニアユースやユース年代になるとJクラブのアカデミーや中高サッカー部強豪校の一員になる」。とはいえ「簡単にはプロの世界に上がれず(あるいは自分の意思で上がらずに)、回り道をするケースがあるということ」。それが日本の特長の一つだと見ている。
一方、反町委員長が監督として率いていた2008年の北京オリンピックでは、長友が大きな国際大会を経験することなく出場。ところが、「北京オリンピック本番に突入した長友は、今の長友とは別人だった。本当に〝若葉マーク〟という感じで、初戦の米国戦は過緊張のあまりミスを連発した」と想起する。
「私はベンチの安田理大にすぐにウォーミングアップを命じた。ピッチの選手は控え組の動きを敏感にキャッチする。アップを始めた選手を見て、誰が交代させられるかの見当もつく。
それをキャッチして『監督は俺を代える気なのか』と発奮してエンジンをかける者もいる。この時の長友はそんなベンチの動きも全く気付いていなかったそうだ。
恐ろしく視野が狭くなっていたわけである。後で長友から『オリンピックがこんなに注目される大会だと思っていなかった』という告白を聞かされたが、代表で戦うことの『重さ』に気づいていなかったのである」
そして反町“監督”が北京五輪後、JFAに提出したレポートについて明かしている。
「その中で『長友の様なオリンピックが世界大会デビューというのは決して好ましくはなく、やはりそこに至るまでに何度かは《世界》を経験していく必要がある』という趣旨を書いた」
同様に今大会、カタールW杯に臨んだ三笘薫が、もう少し早く世界に触れていれば――と反町委員長は感じたそうだ。
一方、前田大然、遠藤航らのパスウェイにも言及。タレントをしっかりプロに引き上げる環境が整い、そこから台頭していった彼らの頑張りにも目をみはる。
反町委員長はそういった“遅咲き”のタレントが出てくる日本の長所を生かしながら、一方、世界のトップに行くためにはJFAの指針とする「17歳でデビュー、10代で初キャップ」という成長速度の“スピード化”も課題に挙げる。
確かにイングランド代表、ドイツ代表、スペイン代表、さらにはブラジル代表など各国サッカー協会は、スーパーエリートをフル代表(国際Aマッチ)で積極的に起用。むしろクラブに還元するような役割を担ってきた。その指針を示し、実行するにはJFAの仕事・責任もあるだろう。
もちろん長友も、三笘もその過程での様々な経験により、現在の活躍がある。カタールW杯で、出場機会を得られなかったのはベテラン選手たちだった。A代表の大舞台では、どうしてもメンバー構成が年功序列になりがちなのも気になるところではある。
多岐にわたるパスウェイを日本の武器に、頂点を引き上げていく。そして裾野が広がっていくのが理想形である。たくさんの人が普段からグラウンドでサッカーを楽しめる環境づくり(町になるとボールを蹴りたくてもその場さえないだけに……)も求められる。