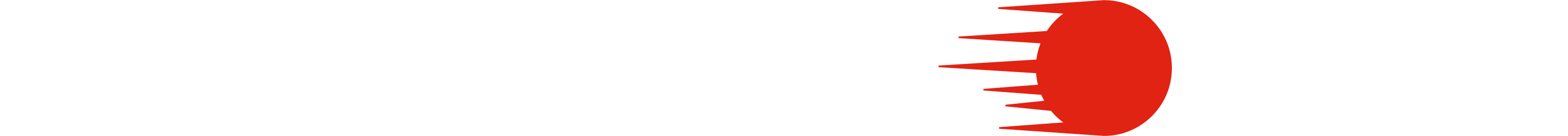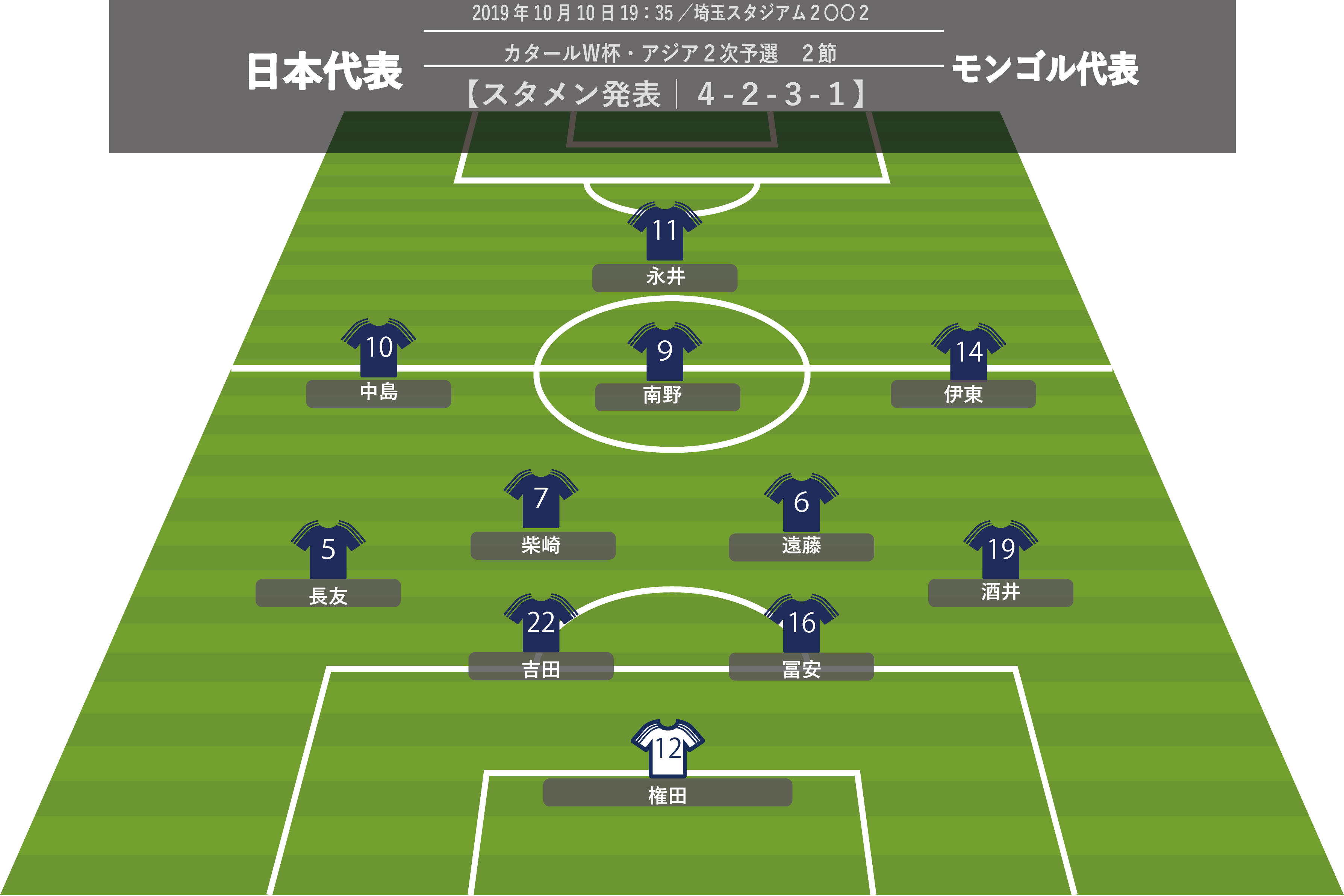【日本代表│検証】西野流「大人のサッカー」に懸けるしかない
 日本代表の長友佑都 写真:徳原隆元/(C)Takamoto TOKUHARA
日本代表の長友佑都 写真:徳原隆元/(C)Takamoto TOKUHARA
ある意味、カラーが映し出された日本代表23人が揃う。
日本代表の西野朗監督がガーナ代表(●0-2)翌日の5月31日、FIFAワールドカップ・ロシア大会に臨む23人を発表した。結局、ガーナ戦に向けて選出された選手からの入れ替えはなし。指揮官は合宿に参加した27人(青山敏弘がその後ケガにより離脱)について、「あくまでもガーナ戦に向けたメンバー」と強調していた。
久保裕也(ヘント)は5月27日まで所属クラブの試合があることが招集されなかった理由の一つだったため、このタイミングで呼ばれるのではないかと予想された。が、「基本的にはこの合宿のメンバーから選ぶが、入れ替えもあり得る」と西野監督の言っていた、「基本的」なメンバー選考に落ち着いた。
落選したのはフィールドプレーヤーで最も年齢が若かった3人。ガーナ戦で与えられた背番号の”重い”順だった。
閉塞感を打破するためにヴァヒッド・ハリルホジッチ前監督が解任されたが、その中心メンバーが選ばれた。指揮官が選んだのは4バックから3バックへのシステムの変化。そもそもわずか1試合しかチャンスがなかったとはいえ、内容的に乏しく、むしろチームは後退したようにさえ思えた。
ただ、選手たちからは、「自発的に取り組めていて、そこは新たに変わった点」(岡崎)、「絶対に勝たないといけない試合だったが、内容的には一定の手応えがあった」(本田)、「劣勢だったとは思わないが、結果を残せなかった」(長谷部)と、少なからずポジティブな声が聞かれた。
23人のメンバーと落選した3人。そこに西野監督のカラーが色濃く感じられる。
Jリーグの柏レイソル、ガンバ大阪を率いた西野監督が、最も重用していた一人が明神智明(現・長野パルセイロ)だった。チームのために戦えて、かつクレバー。自分の言葉を持っていて、それを相手の立場になって伝え、まとめていく力を持っていた。
G大阪では宮本恒靖への信頼も変わらなかった。彼もまた理論的に物事を構築できて、独自のサッカー観を持っていた。ある意味、西野監督はピッチの指揮官として、宮本に統率を任せていた。そしてG大阪に2005年のJリーグ初優勝をもたらした。
ストライカーや司令塔タイプは他にいるが、そういったクレバータイプの柱を据えて、そこからチームを作っていった。
チーム全体を俯瞰できるタイプ。そんな大人な選手を好む。ヴィッセル神戸、名古屋グランパスを率いたとき、そういったタレントを見出せなかったことも低迷を招いた要因の一つと言えた。
今回、そういった、サッカーへの特別なこだわりを持つ23人が選ばれたと言える。
何も落選した3人にこだわりがない、クレバーではない、と言っているわけではない。キャンプに参加していた26人の中で見ると、この23人はワールドカップへの”こだわり”が突出していた。燃えるような情熱を隠さず、言葉でも表現していける「個」を持っている。
とはいえ西野ジャパンに勝利を収めた平均年齢23.3歳のガーナ代表は、逆に若さを前面に押し出し、勝負どころでは徹底的に1対1を仕掛けてきた。むしろ西野監督はそういった”やんちゃ”を、ある意味、排除したとも言えた。
過去5大会の中で最も平均年齢が高い(28.3歳)ことがクローズアップされるが、その実(じつ)もまた「大人のチーム」だ。
ある意味、西野監督らしく、そのカラーが映し出された23人と言えるのではないだろうか。
指揮官は最低限の約束事を提示し、選手同士のコミュニケーションによる相乗効果を期待しているのではないか。本田も「守備陣はポジティブ、攻撃陣はネガティブに受け止めている。あと3週間、そこを擦り合わせる必要がある」と改善点を挙げていた。選手に委ねている部分は多い。
何かを要求する。その時点で、責任も生じる。そういった関係性を求めていることが分かる。その高め合う関係に、落選した3人は入りきれなかった。それはそれで、十分な落選理由なのかもしれない。
もちろん、だから勝てる、それが良いというわけではない。ワールドカップ本番では、ガーナ戦で露呈したように、西野監督が戦術のディテールにこだわらずにいることが命取り=あっけない敗戦にもなりかねない。閉塞感をいまだに脱し切れずにいるのは、結局のところ、若いパワーによる突き上げが不足しているからかもしれない。
そこはリオ五輪代表監督だった手倉森誠、東京五輪監督の森保一、両コーチの腕の見せ所にもなる。柏やG大阪で名参謀に恵まれてきたこともまた、西野監督の成功の秘訣だった。
日本代表は2日に発ち、インスブルックとカザンで合宿をしながらスイス(9日)、パラグアイ(12日)と親善試合を行ない、19日にワールドカップのグループステージ初戦、コロンビア代表戦を迎える。
西野流の大人のスタイルに、懸けるしかない。
取材・文:塚越始
text by Hajime TSUKAKOSHI